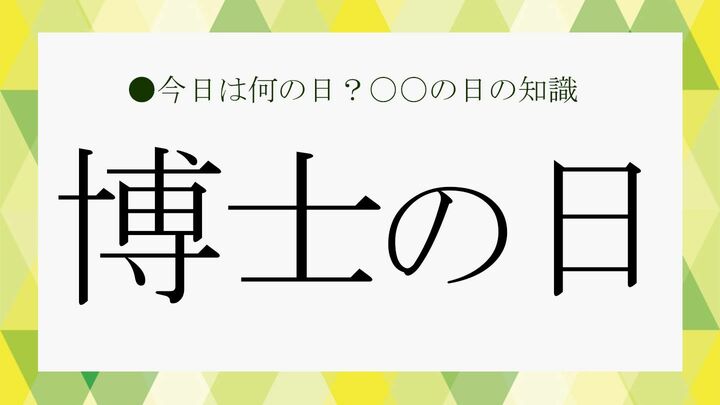【目次】
【「博士の日」とは?】
5月7日は「博士の日」です。あまり馴染みがないかもしれませんね。詳しく見ていきましょう。
■「読み方」
この場合の「博士」は、「はくし」と読みますよ。「はかせ」とも読みますが、この違いについては、のちほど詳しく解説します!
■なぜ5月7日? 日付の「由来」は?
1888(明治21)年の5月7日、「おしべ」「めしべ」「花粉」という言葉をつくったことでも有名な植物学者の伊藤圭介さんや、東京大学初の日本人理学部教授で物理学専門教育の草創期を支えた山川健次郎さんなど、全25人に日本初の博士号が文部省(現・文部科学省)より授与されました。この時、法学博士、医学博士、工学博士、文学博士、理学博士の5種類の博士号が設けられました。これを記念してつくられたのが、「博士の日」です。
【ビジネス雑談に役立つ「日本」と「世界」の「博士」の雑学】
■そもそも「博士(はくし)」って何?
「博士」という言葉が表す意味は、主に3つです。
1) 学問やその道の知識にくわしい人。博士(はかせ)。例:「お天気博士」「物知り博士」
2 )学位の「博士(はくし)」。俗称として「はかせ」と言われることも。例:「博士号」「文学博士」
3 )律令制の官名。博士(はかせ)。
おわかりですか? 同じ「博士」という言葉でも、「はかせ」と「はくし」では意味が異なるのです。博士(はかせ)はもともと、3の、大化の改新以来の伝統的な教官の官職名を指しており、学位・称号といった意味はもっていませんでした。教育者としての役割を担い、恐らくはここから転じて「魚博士」や「お天気博士」など、その道の知識に秀でた人を「〇〇博士(はかせ)」と呼ぶようになったのです。
一方で、明治になって定められた「学位」が博士(はくし)です。1873(明治6)年の「学制」の改定で、博士 (はくし) が学士および得業士とともに学位とされ、1920(大正9)年の学位令により、博士は唯一の旧制の学位となりました。
当時の博士号は論文の提出によるものではなく、教育への貢献を評価されたものでした。論文審査による本格的な博士が生まれたのは、日本人初となった25人の博士が誕生した1888年から3年後の、1891(明治24)年から。現行の学位制度では、大学院博士課程の5年以上の課程修了者、または修業年限5年の博士課程の後期3年以上の課程修了者で、当該大学院の行う博士論文の審査および試験に合格した者、または博士課程を修了した者と同等以上の学力を有する者で論文審査に合格した者に博士号が授与されます。つまり、「博士(はくし)」の学位を得るためには、論文の提出・審査合格が必須となっています。
また、当初は「博士」の上に「大博士」という学位がありましたが、該当者がないまま1898(明治31)年に廃止されたそうです。ちなみに博士号(はくしごう)とは、日本における最高学歴で、一般的には「Doctor(ドクター)」と呼ばれます。
■日本で「博士(はくし)」は何種類?
日本では1887(明治20年)年に公布された「学位令」で、法学博士・医学博士・工学博士・文学博士・理学博士の5種類の博士が設けられました。その後、博士学位は19種類まで増えましたが、1991年の制度変更で廃止されました。
現在は「博士(文学)」などと専攻分野をカッコ内に表記し、その数は優に100を超えています。
■「博士号」はわかった…では「学士号」は?
4年生大学の学部で単位を取得して卒業すると、「学士号」を取得できます。大学院に所属する「院生」に対し、「学部生」と呼ばれることもありますね! また、国内の企業や団体では、採用条件を「大卒以上」、つまり、学士以上としているケースもあります。英語表記では「Bachelor(バチェラー)」。大学を卒業する以外にも、独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構が実施する試験を受けて合格すれば、学士の学位が認められます。
■「修士号」は?
大学の学部を卒業して進学する大学院には、「修士号」を得られる課程があります。修士号は、大学院修士課程(あるいは博士課程前期)で修士論文を提出し、研究実績を認められて課程を修めた人が得られる学位です。「大学院は行ったけど、2年間だけで、博士課程(後期)には行かなかった」と言う人が所有している学位が「修士」です。英語では一般的に「Master(マスター)」と呼ばれます。
つまり、「学士号<修士号<博士号」の順に、専門性が高くなるというわけです。
■「博士(はくし)」を英語で表すと?
博士の学位には「Doctor of Philosophy」とその略である「Ph.D.」が使われます。直訳すると「哲学博士? ん?」となりますが、「Philosophy」には「高等な学問」という意味があり、この場合、すべての科目の上に君臨する上位の称号、つまり専攻分野に関わらず「博士号」を意味します。日本では前述の通り、「博士(文学)」などと専攻分野をカッコ内に表記しますが、英語ではこういった表記はしません。
「Doctor」(略:Dr.) 」も博士号を示す略称ですが、この語には「医者」という意味が含まれるため、医者と混同される可能性があります。ですから、日本で博士号を取得した場合は、「Ph.D.」 を名乗るほうが誤解されることが少ないと言えます。
■学問に関連する記念日
・「植物学の日」:4月24日
「植物学の日」は、植物学者である伊藤圭介が日本初の博士号を受けたことに由来します。だから「植物学の日」と「博士の日」は、同じ日なのですね!
・物理の日 :11月3日
11月3日は「文化の日」で祝日ですが、「物理の日」でもあります。「物理の日」は、物理学の進歩と普及を目指してさまざまな活動を行う一般社団法人日本物理学会が制定した記念日です。一般の人や青少年に向け、物理学を広く普及し、啓発活動をより活発化させることが目的。日付は、湯川秀樹博士が日本人初のノーベル賞(物理学賞)を受賞することが決定し発表された日(1949年11月3日)にちなむとともに、日本で発見され日本人が初めて命名した元素「ニホニウム」の原子番号113に由来します。
***
昔から日本では、優秀な子どもを讃える最上級の言葉として、「末は博士か大臣か」というフレーズが使われていました。学問を深く学び「博士号」を取得することは、それ程、高い評価と敬意を集めるものだったのです。「博士の日」は、「知」を愛し、学問を追求するすべての人々にとって、特別な日です。現在、私たちが便利で快適な日常を送っていられるのも、学問の進歩を支えてきた研究者たちのおかげ。彼らへの感謝と敬意を表す日として、この日を大切にしたいものですね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) /一般社団法人日本記念日協会(https://www.kinenbi.gr.jp) :