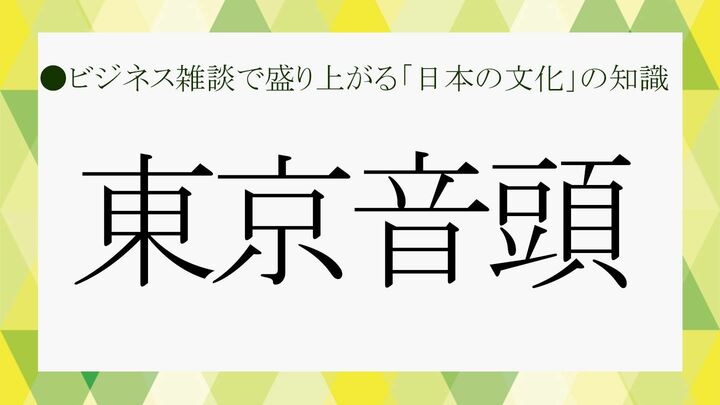【目次】
【「東京音頭」が誕生したのはいつ?「歴史」】
■「いつ」つくられた?
「ハア~踊り踊るなら チョイト東京音頭(ヨイヨイ)」で始まる『東京音頭』。「盆踊り」と聞いて、多くの人が連想するこの曲が誕生したのは、昭和初期です。西条八十 (やそ) が作詞し、中山晋平 (しんぺい) が作曲。当初は『丸の内音頭』という曲名でした。
■誕生した「理由」は?
この曲が誕生した背景には、1929(昭和4)年の世界経済の大パニックや、中国大陸へ広がる戦火などがありました。大きな発展を遂げてきた日本にも不況の波が押し寄せ、庶民は重苦しい気分を転換させたがっていました。
こうした社会の空気を読み取った丸の内周辺、有楽町界隈の飲食店経営者たちが、「丸の内で音頭をつくり、人々を盛り上げよう」という企画を考えたのです。当時の日本には、地方ごとにそれぞれの地域で根付いてきた音頭があるにも関わらず、東京にはなかったからです。これが東京音頭の原型です。やがて「丸の内音頭」は、東京一帯の祭りで、盆踊りのときに流れるようになっていきました。
■全国的に知られるようになったのはなぜ?
「丸の内音頭」は、作曲家であった中山晋平が九州へ旅行した際に聞いた『鹿児島小原良 (おわら) 節』にヒントを得て、1933(昭和8)年に、三島一声と勝太郎の組合せで、新しく『東京音頭』としてレコード化されました。そして、祭りのときだけでなく、百貨店や劇場などでも流されたほか、レコード会社の社員が各地で踊り方を指導するなどして宣伝に力を入れたこともあり、『東京音頭』は「新民謡」というジャンルで、東京のみならず全国的なヒット曲になったのです。
【ビジネス雑談にも役立つ「東京音頭」と「盆踊り」の雑学】
■そもそも「音頭」って何?
「音頭」とは日本音楽の用語で、「おんどう」とも呼ばれます。雅楽の合奏では各管楽器の首席奏者です。西洋音楽の指揮者を指すこともあり、ここから大勢で歌うときなどに、調子を揃えるために、先に歌い出して調子をとり、全体を導くことを「音頭をとる」といいました。『東京音頭』のように、大勢が歌曲に合わせて踊ることも「音頭」と表現します。
■「東京音頭」の歌詞には都内各地の地名が
実は『東京音頭』の歌詞は10番まであるのを、ご存知でしたか? 盆踊りで流れるのは、主に5番まで。上野、銀座、隅田のほか、東京各地の地名が歌詞に折り込まれています。
■「東京音頭」はご当地音頭ブームの火付け役に
『東京音頭』が全国的にヒットしたことを受け、北海道音頭、東海音頭、四国音頭など、地域活性化を狙って同じメロディーで歌詞が異なる「ご当地音頭」が相次いで発売されました。
■ヤクルトスワローズの応援曲が東京音頭なのはなぜ?
プロ野球チーム・ヤクルトスワローズの本拠地は、東京都新宿区にある神宮球場です。『東京音頭』を球団の応援歌にするよう考案したのは、ヤクルトスワローズの名物応援団長・岡田正泰さんだったといわれています。
1980年代前半に、少しでも野球場にいるファンの数を多く見せるために、苦肉の策として生まれたのが、傘を使った応援でした。やがて「東京音頭とビニール傘の応援スタイル」がヤクルト独自のスタイルとして定着したそうです。ノリがよく、歌詞が覚えやすい『東京音頭』は、応援歌にピッタリだったのですね。
■「東京音頭」と「大東京音頭」の違いとは?
『大東京音頭』は東京12チャンネル(現・テレビ東京)の開局15周年記念事業として、一般から公募した総踊り唄です。多くの応募作品の中から愛知県の滝田常晴氏の詞が選ばれ、歌いやくすてスケール感のある曲を遠藤実氏が作曲しました。レコード会社10社による競作合戦となり、歌謡界を盛り上げましたが、橋幸夫と金沢明子のビクター版がいちばんヒットしたそうです。
■「盆踊り」って何のために踊るの?
「盆踊り」は、お盆の時期にお迎えした、精霊(しょうりょう)と呼ばれるご先祖様の霊をもてなし、一緒に過ごした後に送り返す行事です。由来は仏教の「念仏踊り」だとされ、一説には平安時代にまで遡るといわれています。「念仏踊り」が「踊り念仏」に発展し、これらがさらにお盆と結びついて、現代の「盆踊り」となりました。
■日本三大盆踊りはどこ?
・阿波踊り(徳島県)
「えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、よいよいよいよい」の掛け声で知られる、徳島の阿波踊りは。踊り子や観客数、規模において日本一の盆踊りです。400年以上の歴史があり、太鼓や三味線、篠笛などの伴奏にあわせ、踊り子たちが徳島市街を踊り歩きます。「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損損」というフレーズも有名ですね。
・西馬音内の盆踊り(にしもないのぼんおどり/秋田県)
秋田県羽後町で毎年8月16日〜18日におこなわれている「西馬音内の盆踊り」には、寄せ太鼓、音頭、とり音頭、がんけの4種類ああります。豊かな実りを願ってご先祖様たちと一緒に踊る行事で、見た目の芸術性が素晴らしいと評価されています。
・郡上踊り(岐阜県)
岐阜県郡上市で毎年7月中旬〜9月上旬まで、約32日間(夜)踊る盆踊りが「郡上踊り」。実に30夜以上にわたって続く、盛大な祭りで、8月13日〜16日には「盂蘭盆会」という徹夜踊りが開催されます。 中世の古い踊りの流れを取り入れつつ、江戸時代から本格的に盆踊りとして広まりました。「春駒」や「三百」「やっちく」「げんげんばらばら」「さわぎ」など10種類の踊りがあり、上半身はTシャツなどでもよいのですが、足元の下駄は必須。下駄を鳴らして調子を高めるのが特徴です。
***
日本には全国に特色豊かなお祭りがあります。「盆踊りならこの曲」と、出身地によって、思い出の歌も多分、さまざま。2021年の東京五輪閉会式では『東京音頭』が流され、各国の選手がノリノリで踊る姿が印象的でした。「音頭」には、人を浮き浮きした気分にさせる、不思議な魅力があるのです。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『江戸のきものと衣生活』(小学館)/『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 前編』(NHK出版)/『NHK2025年大河ドラマ完全読本 べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺』(産経新聞出版)/『日本髪の描き方』(ポーラ文化研究所)/『お江戸ファッション図鑑』(マール社)/『見てきたようによくわかる 蔦屋重三郎と江戸の風俗』(青春文庫)/『江戸の衣装と暮らし解剖図鑑』(X-Knowledge)/『一日江戸人』(新潮文庫)/『蔦屋重三郎 江戸を編集した男』(文春新書) :