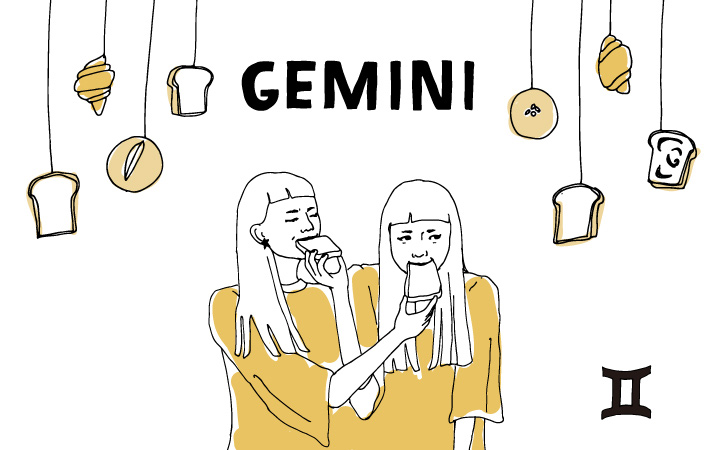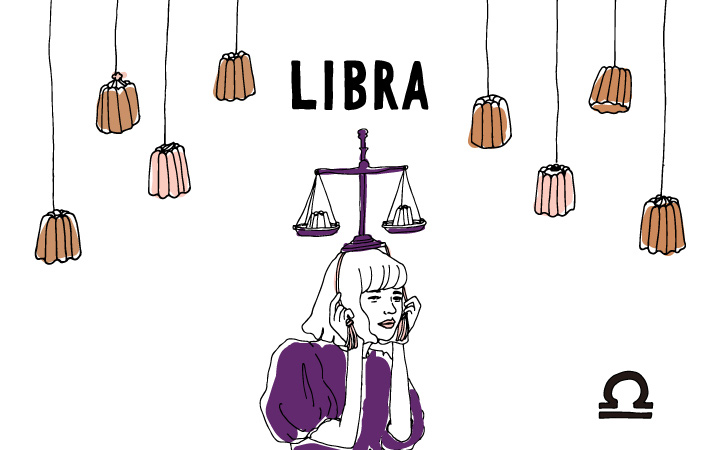海外ならではの挑戦的な作品は、「修業」。置かれている現状に甘えることなく、自分を律するために
カメラの前に現れると、たちまち「物語」が紡がれ始める。その繊細な手の動きに、背中の佇まいに、そして探るような視線の先に―。オダギリジョーさんが国内外のつくり手を魅了し、観客を作品の世界へと深く引き込んできた所以だろう。中国を代表する名匠ロウ・イエ監督も、最新作『サタデー・フィクション』の脚本を執筆する過程で、オダギリさんの写真を傍らに貼り、インスピレーションを受けていたという。

「光栄なことですね。海外ならではの挑戦的な作品は、僕にとって、何年かに一回は続けなくてはならない『修業』みたいなもの。伝え方が難しいのですが、日本で仕事を続けていると、自分は甘やかされていると感じることが多いんです。長くやればやるほど、キャリアや立場ばかりが上がっていく一方で、芝居が良くなっていく感覚はない。年下のスタッフが増え、怒られることやダメ出しされることもなくなります。ぬるま湯とも言える環境にいることを自覚して、甘えることなく自分をちゃんと律していかないと」
研鑽の場として臨んだ本作では、太平洋戦争直前の上海を舞台に、各国のスパイが暗躍。世界の名優が集結する中、オダギリさんはストーリーの鍵を握る暗号通信の専門家を演じた。
「2か月の撮影期間を、上海で過ごしました。異国の地では、僕を知らずに『こいつは誰なんだ?』と思いながら見ている人も少なくないでしょうし、だからこそ、芝居で認めてもらいたい、納得させたいという思いが強く立つ。それに、外国人の俳優を相手にすると、言葉のニュアンスに頼ることなく、純粋に本質でぶつかり合えるというか。すごく新鮮な気持ちに戻してもらえるんです」

ここから先は、人間としてどう生きていくか。五感で人生を感じていきたい。

近年は演出、脚本、プロデュースといった領域でその才能を発揮。作品づくりへの確かな情熱を秘めながらも、「自分で監督するときは、現場が苦しくてしょうがないんですよ」と、心中を繕わない。
「まだとても現場を楽しむ余裕なんて、もてません。脚本では好きなことを自由に書けても、いざ映像にしようとすると理想のロケ場所さえ見つからない。活字の想像力には勝てないな、脚本より面白くなっているんだろうかとプレッシャーの毎日です。最近は撮影中でもご飯が喉を通るようになったものの、40代初めに撮った長編の初監督作『ある船頭の話』では、丸一日トイレに行くことすら忘れていたほどで。体にはよくないです(笑)」
心身を削りながら生まれた同作は、第76回ヴェネツィア国際映画祭でヴェニス・デイズ部門に選出。現在公開中の出演作『サタデー・フィクション』は、コンペティション部門で評価された。
「自分が信頼する方々に認めてもらえるのは本当に嬉しいことです。でも、自分自身に満足した経験はほとんどありません。もっとこうしたほうがよかったな、という後悔が頭をよぎるので」
謙遜ではなく、謙虚に上を見ているからこそ出る言葉だろう。この先大事にしたいことを尋ねると、「人間としてどう生きていくか」と、真っ直ぐな答えが。
「人生って仕事がすべてではないし、大切なことはほかにたくさんあると思うんです。時には携帯を眺めて終わってしまう一日もありますが、せっかくなら少しでも現実と触れ合い、五感を刺激したい。美味しいご飯を食べに行く、外の風を感じるだけでもいい。過去の47年をなぞるより、人生を豊かにしてくれるものに時間を使っていきたいと思います」

関連記事
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- BY :
- 『Precious12月号』小学館、2023年
- PHOTO :
- 長山一樹(S-14)
- STYLIST :
- 西村哲也
- HAIR MAKE :
- 砂原由弥・シラトリユウキ(UMiTOS)
- EDIT&WRITING :
- 福本絵里香(Precious)
- 取材・文 :
- 佐藤久美子