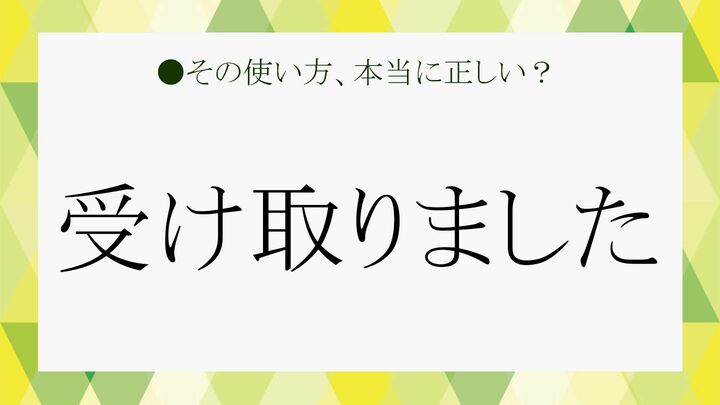【目次】
【「受け取りました」を深く理解するための「基礎知識」】
大切な文書ファイルが添付されたメールや、緊急性の高い宅配便などを誰かに送ったとき、「きちんと届いたかな…?」と心配になるものです。そんなとき、先方から届く「受け取りました」の報告メールはありがたいですよね。逆もまた同じ。メールや送付物を受け取った際には、できるだけ早く受け取ったことを報告するメールをして、先方の不安を取り除くよう配慮するのがビジネスマナーといえるでしょう。
■「受け取りました」を敬語にすると?
「受け取りました」は、このままでも正しい敬語表現です。
現在、「敬語の指針」(文化審議会答申)によると、敬語は〈尊敬語〉〈謙譲語I〉〈謙譲語II〉〈丁寧語〉〈美化語〉の5種類に分けられています。「受け取りました」を分解すると、動詞「受け取る」+助動詞「ます」+助動詞「た」となりますが、「ます」は丁寧語にあたります。従って、「受け取りました」は正しい敬語表現であるといえるのです。
■「受け取りました」をもっと丁寧な敬語表現にすると?
ただ、助動詞「ます」は文章全体を丁寧にする敬語ですが、尊敬語や謙譲語のように「送ってくれた人」に対する敬意を示すことはできません。社内のやり取りであれば問題ありませんが、取引先や目上の人に対しては、尊敬語や謙譲語を用いた敬語表現がふさわしいものです。
「受け取りました」をもっと丁重度の高い表現にすると、「頂きました」となります。「頂(いただ)く」は「受け取る」「もらう」の謙譲語。へりくだることで相手への敬意を示すことができます。ちなみに、ひらがなでも間違いではなりません。
■さらに丁寧な敬語表現は?
「頂きました」をさらに丁重な敬語表現にすると、「拝受(はいじゅ)しました」となります。「拝受」の「拝」という漢字は、「拝(おが)む」という訓読みからもわかるように、自分のことをへりくだる意味を含んでいます。ここから「拝受」は、「つつしんで受けること。ありがたく頂戴すること」という意味となります。「拝見」「拝読」「拝借」なども同様の謙譲語です。
「拝受しました」をさらに丁寧に表現すると、「拝受いたしました」になります。「二重敬語では?」と思うかもしれませんが、大丈夫。そもそも二重敬語とは、「ひとつの語において、同じ種類の敬語を二重に使ったもの」で、一般的に適切ではないとされています。「拝受いたしました」の場合、「拝受」は「受け取るという行為が向かう先」に対する敬語〈謙譲語I〉。「いたしました」は、聞き手に対する丁寧な表現である〈謙譲語II〉に相当します。敬語の種類が違うため、二重敬語にはならないのです。
例えば、取引先が送ってきたメールを、あなたが受け取ったかどうか、上司に聞かれたとしましょう。「拝受いたしました」と答えることで、取引先(受け取るという行為が向かう先)への敬意を表すと同時に、上司(聞き手)への敬意も示したことになるのです。「拝受いたしました」は最上級の敬語表現ですから、逆にいえば社内で使うには少々大げさすぎる言葉だともいえます。ごく親しい取引先に対しても、少し堅苦しい印象になってしまうかもしれませんね。
【「受け取りました」の「類語」「言い換え」表現】
■「受領しました」
「受領」は「受け納めること。金や物を受け取ること」という意味の言葉ですが、敬語のニュアンスはありません。ただし、「受け取りました」同様、丁寧語が使われた敬語表現です。丁寧さの度合いは「受け取りました」と同等に見えますが、現代語では「受け取る」などの動詞よりも「受領」などの名詞を使ったほうが、丁重度が高くなるため、「受領しました」のほうが「受け取りました」より丁寧な表現であるといえます。
相手が取引先や目上の方であれば、「受領いたしました」と謙譲語を用いた敬語表現にするのが適切でしょう。
■「頂戴しました」
「頂戴(ちょうだい)」は「受け取る」や「もらう」を意味する謙譲語です。「拝受」と同じように使えますが、「お土産を頂戴しました」のように、どちらかといえば「受け取る」よりも「もらう」という意味合いで使われることが多い言葉です。状況によっては「(私が)もらいました」の意味に受け取られてしまうケースも考えられますので、注意が必要です。
【具体的なシーン別「そのまま使える例文」8選】
幅広いシーンで使用できる敬語表現は、「受け取りました」や「頂きました」ですが、シーンに応じた表現をいくつかご紹介します。
■「荷物」を受け取った場合
・「先ほど商品サンプルを受領しましたこと、ご報告いたします。ありがとうございました」
・「お送りくださった宅配便を確かに受け取りました。早々のご対応をありがとうございます」
■「資料」「書類」を受け取った場合
・「本日、見積書を受領いたしました」
・「お送りいただいた資料、拝読いたしました」
・「詳しい資料を頂戴しました。ありがとうございます」
「拝受」は「受け取った」ことだけを意味する謙譲語です。メールに添付された文書や送付されてきた書類の「内容を確認した」ことを伝えたい場合は、「拝読しました」が適切です。
■「メール」を受け取った場合
・「確かにメールを受け取りました。ありがとうございます。ご質問につきましては、改めてご返答申し上げます」
・「ご連絡を確認いたしました。直ちに上司に伝えます」
・「メールを拝受いたしました。ご提案につきまして、早速社内で検討させていただきます」
■「手紙」や「品物」を受け取った場合
「受け取る」の敬意を高めた言葉に、「落手(らくしゅ)」「落掌(らくしょう)」があります。漢語的な表現で、手紙や文書で使います。あらたまった手紙で返事をするときや、特に配慮したい相手宛のメールで使うとよいでしょう。
・「本日、お手紙を落手いたしました」
【「確認メール」のビジネスマナー】
ビジネスのやり取りでは、今や電話よりもメールが主なツールとなっています。メールは確かに便利ですが、顔が見えないぶん、言葉の微妙な選択で誤解が生まれたり、相手を不快にさせたりしてしまうことも少なくありません。「受け取りました」を知らせる確認メールを送る際に、覚えておきたい基本的なマナーをご紹介します。
■できるだけ早く返信する
ビジネスメールのマナーとして、受け取ったメール本文に「質問したいことがある場合だけ返信する」と認識している人も多いようです。社内や内輪でのやり取りであれば問題ないのかもしれませんが、取引先を含め目上の方からのメールには、質問がなくても「受け取った事実をできるだけ早く返信する」のがマナーです。
もし、メールの内容を精査できない、あるいはすぐに対応できない場合であれば、「受け取ったけれど、回答には時間を要す」旨をお伝えします。その際、「○月△日までに」など、回答の目安をお伝えすると丁寧な印象になると同時に、先方の不安を取り除くことができます。「メールの内容について、上司の確認が取れてから返信しよう」といった姿勢は禁物です。
■報告メールの「件名」はどうする?
受け取ったメールに返信する場合、件名はそのままにしておきましょう。自分では丁寧なつもりで「拝受いたしました」など件名を変更してしまうと、先方はどのメールに対する返信なのかわからなくなってしまいます。かえって誤解や間違いを誘発する原因となりかねませんので、「Re:」以下の件名や「返信画面に引用される本文」は変更しないのが正解です。
複数人が宛先に入っているメールで、自分が〈CC:〉に入っている場合は、基本的に返信の必要はありません。ただし、「ご了承いただけるのであればご返信ください」などと書かれた場合は、〈CC:〉のほかのメールアドレスも残したまま返信します。
■感謝の言葉を添える
メールはとかく事務的な文章だけになってしまいがち。「お忙しいなか、詳細な資料をありがとうございました」「迅速なご対応に感謝申し上げます」など、相手への感謝の気持ちをひと言添えることで、コミュニケーションが円滑に進みます。
***
敬語は「丁寧なら丁寧なほどいい」という単純なものではありません。「受け取りました」という意味のフレーズも、相手との関係性によって表現が自在に変化します。正しい敬語表現である「受け取りました」から「拝受いたしました」まで、丁寧さの異なる表現から、状況にふさわしい言葉をセレクトしたいものですね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:「敬語の指針」(文化審議会答申)/『デジタル大辞泉』(小学館)/『明鏡国語辞典』(大修館)/『敬語マニュアル』(南雲堂) :