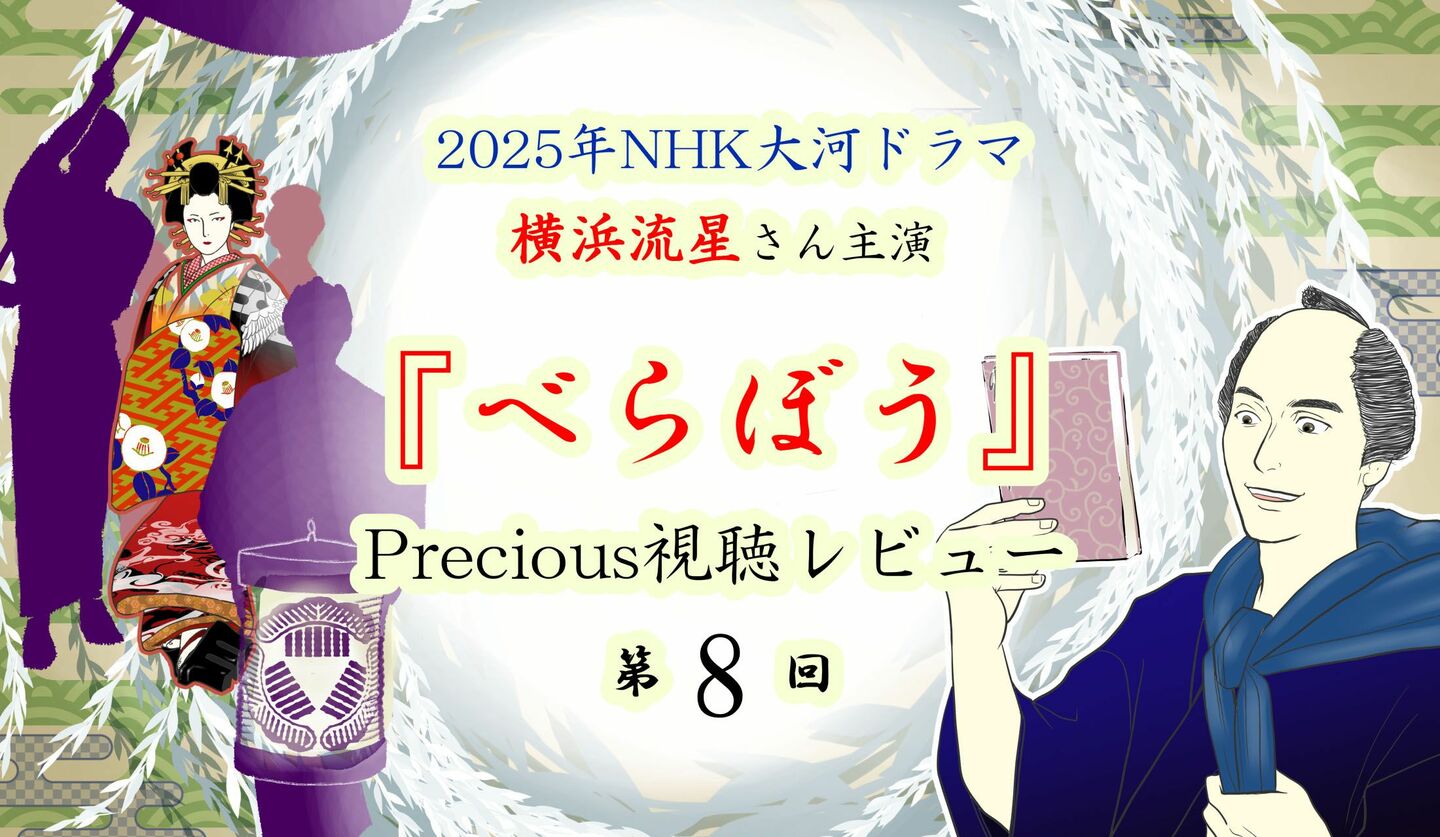【目次】
- これまでのあらすじ
- トップオブ花魁「五代目瀬川」の身請け代は?
- 「五代目瀬川」の「花魁道中」にはドラマ制作陣のこだわりが!
- 『一目千本』『雛形若菜初模様』で吉原遊女は「江戸の華」に
- 第8回のタイトル「逆襲の『金々先生』とは?
- 次回『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第9回 「「玉菊燈籠(たまぎくどうろう)恋の地獄」のあらすじ
【これまでのあらすじ】
大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』は、天下泰平、文化隆盛の江戸時代中期を舞台に、親なし金なしの蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星さん)が、その企画力とプロデュース力で「江戸のメディア王」にのし上がっていく物語です。第7回までの蔦重は、まだまだ駆け出し。なんとか版元としての第一歩を踏み出そうと奮闘中、といったところ。さて、第8回はというと…。
第7回で、偽板づくりで検挙された鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)に取って代わって地本問屋の「仲間」となるため、蔦重が提示した条件は、「今までの倍売れる細見をつくること」。そして、蔦重の吉原細見『籬(まがき)の花』は大評判になりました。細見を薄くして価格を抑えるとともに懐に入れても持ち運びやすくする工夫と、揚代の安い河岸見世までを網羅した情報量の多さや見やすいレイアウト…と考え尽くされ、練りに練られた出版物としてもそうとうな代物ですが、それ以上に人々の関心を引きつけたのは、花の井(小芝風花さん)改め、「五代目瀬川」の襲名でした。
この襲名は、少しでも蔦重の力になろうと、不吉な名跡とされていた「瀬川」継承を決めた、花の井自身の決断によるもの。
このとき、SNSには「さらっと蔦重のピンチを救う花の井がまさにヒーロー!」「少しでも蔦重の役に立ちたい花の井がけなげ」といった声が溢れました。
蔦重が細見を売り、瀬川が客を引き寄せる…ふたりの息の合ったタッグによって、大盛況となる吉原の町。そして第8回、人々は、瀬川の「花魁道中」に感嘆のため息を漏らすのでした。
今回は第8回で登場したこの「五代目瀬川」の「花魁道中」を中心に、江戸中期の花魁ファッションについて解説します。
【トップオブ花魁「五代目瀬川」の身請け代は?】
■「五代目瀬川」襲名は、吉原全体が沸き立つビッグイベント
「瀬川」は吉原でも指折りの大見世「松葉屋」に代々伝わった名跡です。この名を継いだ花魁は9人いましたが、その多くが高額で「身請け」され、松葉屋はそのたびに財をなしたといわれています。
「身請け」とは、客が女郎の抱え主である妓楼への前借金などを払ってやり、娼妓(しょうぎ)の稼業から身をひかせること。多くの場合、そのあとは身請け人の妻や妾(めかけ)となりました。
身請けにかかる費用は瀬川クラスだと1000両超え。令和の現在と江戸時代の貨幣価値を単純に比較することはできませんが、目安として江戸時代のお米の値段が[米1石(約150kg)= 1両]とすると、お米5㎏を4000円(2025年2月現在)で計算すると、1両は現在の12万円に相当します。つまり、1000両は1億2000万円。大金です!
■「花魁道中」は、なぜ「道中」?
「道中」とは「旅」のこと。吉原では位の高い女郎と遊ぶ際、いきなり女郎のもとを訪ねることは許されませんでした…という話は『べらぼう』でも語られていましたね。
客はまず、引手(ひきて)茶屋と呼ばれる、客に女郎を紹介する茶屋にあがり、そこへ女郎を呼び出して宴会を開き、そのあとで女郎屋に同行するのが決まり。その際、女郎が客の待つ引手茶屋へ、さらに引手茶屋から女郎屋へと行き来することを「道中」と呼んだのです。
お供は、若い振袖新造ふたりに、身の回りの世話をする禿(かむろ)と呼ばれる見習いの少女がふたり、そして荷物持ちの男衆。そんな面々で行列を仕立ててゆっくりと練り歩きます。最初は人数も少なくシンプルなものでしたが、やがて「花魁道中」そのものが吉原の大きな売り物となり、「大名行列」をも思わせる、ド派手なものとなっていきました。
■吉原花魁の象徴、「外八文字(そとはちもんじ)」
女郎が郭内を道中するときの履物は、廓(くるわ)独特の「三枚歯下駄(さんまいばげた)」。半円を描き大きく蹴り出すように進めた足を、最後につま先を外側に向け踏み込みます。こうすることで足元が「逆ハの字」になることから「外八文字」と呼ばれました。足をぐっと踏み開くため、着物の裾が割れて覗く襦袢(じゅばん)や白い肌が艶っぽいと評判だったそうですよ。下駄の裏側を見せるように力強く歩くのも特徴です。
それに対して、京都の島原遊郭などでは、つま先を内側に向け、下駄の裏側を見せないよう、しとやかに歩く「内八文字(うちはちもんじ)」が主流でした。
【「五代目瀬川」の「花魁道中」にはドラマ制作陣のこだわりが!】
番組公式インスタによれば、花ノ井を演じる小芝風花さんは、瀬川を襲名する前の花魁道中と襲名したあとの第8回の花魁道中とでは、「表情や歩き方を変えるなどの工夫を重ねた」そうです。どちらもそれぞれ魅力があり、凛と美しい姿にうっとりしますが、その一方で、「それにしても今回のドラマの花魁道中、なんだか少し地味じゃない?」と思った方はいませんか? そうなんです! これこそが、『べらぼう』演出陣のこだわり。確かな時代考証に基づいているからこそなのです。
『べらぼう』の脚本を手掛けているのは、『JIN-仁-』(TBS系列)や『大奥』(NHK総合)などでも知られる脚本家・森下佳子さん。『JIN-仁-』に登場する花魁・野風(中谷美紀さん)による華麗でゴージャスな「花魁道中」を記憶している人も多いのでは?
実は『JIN-仁-』の主人公・南方仁(大沢たかおさん)がタイムスリップしたのは1862(文久2)年。『べらぼう』第8回の舞台である1775年とは、87年の隔たりがあります。約260年も続いた江戸時代は、その長い間に文化やファッショントレンドも大きく変化していたのです。
花魁ファッションの変化
・体の前で結んだ帯は、時代の経過と共に、長く豪華に
第8回で瀬川花魁が身につけた帯は丈も短くこじんまりしていますが、江戸後期に向けて、『JIN-仁-』の野風さんの花魁道中のときのように、帯は次第に長く、豪華になります。俎板帯(まないたおび)と呼ばれる、幅広で厚い板状の帯には、当時の贅が尽くされていました。
・髷(まげ)は大きく、簪(かんざし)の数も増えていく
瀬川の髪には、透かし彫りが施された光輪櫛が3枚と前挿し簪は左右に3本ずつ。うしろ挿しの簪は左右に1本ずつ。後頭部の髷も小さめですが、後期になると髷が巨大化。蝶の羽のように広がった「伊達(横)兵庫」と呼ばれる盛り髪に、後ろ挿し簪も6本、8本と増えていきます。
・華やかな打掛けの枚数は増え、裾には分厚い綿が入ったフキが幾重にも!
江戸後期になると、着物のいちばん上にはおる「襠(しかけ。仕掛とも)」と呼ばれる織物の打掛けには、分厚い「袘(ふき)」が入ります。袘とは、着物の裾に綿を仕込んで厚みを出した裾回しのこと。打掛け自体にも、立体的に盛り上がった「肉入り刺しゅう」が施されることが少なくありませんでした。
これらの装飾によって、花魁の衣装はよりゴージャスに、より華やかに、より人目を惹きつけるものとなっていきました。
ドラマ『JIN-仁-』の野風に代表される、私たちが見慣れた「花魁道中」は、実は江戸後期のもの。これに対して、江戸中期の花魁ファッションを忠実に再現しているのが、今回の『べらぼう』なのです。簪の数や衣装のボリューム的には少々地味な印象があるかもしれませんが、『日本髪の描き方』の著者である撫子凛さんに感想を伺ったところ、「江戸中期の花魁道中は、帯や打掛けもあまりゴテゴテしておらず、むしろ私好み!」なのだそう。確かに、凛として美しい小芝風花さんの「花魁道中」は、一時代を築いた花魁のプライドと風格を十分に感じさせるものでしたね。
■日本のネイルの歴史は意外と古い
さて、第8回では、「五代目瀬川」の襲名により吉原が賑わう一方で、休む間もなくやってくる客をさばききれない瀬川、そしてほかの女郎たちも、次第に疲弊していく様がリアルに描かれています。
強蔵(つよぞう/精力旺盛な客)に疲れ果て、キセルをふかす瀬川の手元とその横顔の艶っぽいこと! そしてキセルを持つ指先は紅で彩られています。女郎は基本、素足と決まっていますが、その足の爪にもペディキュアが施されていたのにお気付きでしたか?
日本におけるネイルの歴史は古く、ファッションとして楽しむようになったのは、平安時代だともいわれています。
■江戸時代のマニキュアの原料は?
当時は貴族階級の間で、鳳仙花(ほうせんか)とほおずきを揉み合わせて爪を赤く染める「爪紅(つまくれない)」が行われ、やがて遊女を通して広く庶民へと広がっていきました。室町時代になると、紅花を使った染色技術が中国から渡来し、江戸時代中期には山形県最上川流域を中心に、紅花の栽培が盛んになります。紅花はやがて化粧にも利用されるようになり、爪に紅を塗るのを「爪紅(つまべに)」、唇に紅を濃く塗る化粧は「口紅」と呼ばれました。
紅花による「爪紅」は鳳仙花よりも色が落ちにくかったため人気は高まりますが、紅花から採れる化粧用の紅はごくわずか。「紅一匁、金一匁(べにいちもんめ、きんいちもんめ)」と言われるほど、高価なものでした。そのため、紅花を使った「爪紅(つまべに)」は、ごく一部の裕福な人々と、吉原の遊女たちのお楽しみだったようです。
【『一目千本』『雛形 若菜 初模様』で吉原遊女は「江戸の華」に】
ご承知の通り、江戸時代のファッションリーダーといえば、歌舞伎役者と吉原の遊女たち。江戸風俗研究家の杉浦日向子さんの『一日江戸人』によれば、江戸の庶民にとって吉原は、銀座の社用族用クラブと芸能界、そしてファッション業界をあわせたような存在だったとか。「吉原細見」は、そんな遊女の特技や趣味、容貌などを記した、ファンクラブの会報のような役割も担っていました。
第4回で蔦重が西村屋とつくった(そして最後にのけ者にされた)『雛形 若菜 初模様』は、遊女たちが最新の着物を艶やかに着こなしてみせる、スタイルブックでした。着物を売りたい呉服屋に入銀させて出版する手法は、今でいう広告タイアップ。着物を売るという目的と同時に、遊女や妓楼、ひいては吉原そのものを廓外に向けて大々的に宣伝する効果ももっていました。そして実は、それ以前に出した『一目千本』にも、蔦重の吉原への思いが表れています。
『べらぼう』第3回に出てきた『一目千本』は、遊女を生け花に見立てた絵本仕立ての遊女評判記。モチーフとなった生け花は、当時の見立絵における流行の題材。武家文官に由来する格調高いイメージを備えていました。また、作画を担当した北尾重正は当代一の浮世絵師であり、その絵は洒脱で優美。当時、吉原の最高ランクの遊女である花魁を、一般庶民が目にする機会はほとんどありませんでしたが、この本で花に見立てられた遊女のイメージは一気に洗練されたものとなり、遊女と吉原は、華やかな江戸文化の象徴、江戸文化の華そのものとなっていったのです。
そして、ドラマの第7回、蔦重が忘八たちの前で啖呵(たんか)を切ったシーンは強烈でした。
「女郎の血と涙がにじんだ金を預かるんなら、その金でつくる絵なら、本なら、細見なら、女郎に客が群がるようにしてやりてぇじゃねぇすか!」「吉原の女はいい女だ。江戸でいちばんだってしてやりてぇじゃねぇすか!」「胸張らしてやりてぇじゃねぇすか!」などなど…。
蔦重からほとばしる熱い思いが、黙して語らぬ花の見立絵に込められていたことがわかるシーンでもありました。そして、その思いが現実となり、やがて、人気の花魁は錦絵の人気モデルとなり、若い女性たちにとってアイドルのような存在になっていきます。「推し」が着ている着物の柄や帯の結び方、簪や小物を真似て、江戸の女性たちは最新トレンドを身につけていったのです。
【第8回のタイトル「逆襲の『金々先生』」とは?】
さて、ドラマ第8回のラストでは、検挙後、『金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)』の出版で復活を遂げた鱗形屋(片岡愛之助さん)が、地本問屋を引き連れて吉原にやってきます。
『金々先生栄花夢』とは、立身出世を夢見た貧乏な主人公が、まさに夢の中で金々先生と呼ばれるまでの大金持ちとなり、人生のバブルと没落を味わう…という物語の青本のこと。それが人気となって鱗形屋は鼻高々、いまいましくも妬ましい蔦重を再起不能にせんとばかりに意気込んでいます。
忘八たちを前に、蔦重の「仲間」入りはなかったことにしてほしいと議論の口火を切ったのは、鶴屋の主人(風間俊介さん)。なんとか仲間入りをさせてほしいと頼み込む蔦重に対して鶴屋の主人の口から出てきたのは、「吉原者は卑しい外道(げどう)。吉原の方々とは同じ座敷にいたくないとおっしゃる方々がいらっしゃる」というセリフでした。他人の口を借りて吉原者を見下す、鶴屋自身の嫌味ったらしい人柄がよく出ていましたよね。
■「忘八アベンジャーズ」がSNSで話題!
これにぶち切れたのが、まず駿河屋の親父さん(高橋克実さん)。そして阿吽(あうん)の呼吸で障子を開けたのは、大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)。鶴屋の首根っこをつかみ上げ、階段から投げ落としてたんかを切る忘八の面々。蔦重は、この騒ぎを困り果てた顔で見守ります。
SNSでは「まさに忘八アベンジャーズ! 絵になるー」「童顔の風間俊介さんに『この赤子面!!』ってディスりが凄い」と話題に。
ちなみに風間さんは、NHK財団が運営するWEBサイト「ステラnet」の『べらぼう』にまつわるインタビューで、「脚本の森下さんが僕に当て書きしてくれたんだなと思って(笑)。『うそくせぇんだわ、お前』というセリフにも、森下さんは僕の特性をよく見ているなぁと感心します」と答えています。イヤな気持ちになっていなくてよかったです。
第9回のタイトルは、素直に解釈すると、鱗形屋が『金々先生栄花夢』で返り咲いて吉原に乗り込む(逆襲)ですが、鱗形屋たちからしたら、結局夢の中でしか出世できない金々先生は、蔦重に重ねたい人物なのかもしれません。そう考えると、いい気になってのこのこと吉原に乗り込んできた鱗形屋を金々先生(たち)が腕っぷしで逆襲した、という意味にも思えます。みなさんはどちらだと思いますか?
はてさて、蔦重の「仲間」入りはいかなる展開を見せるのでしょうか。今後の展開にますます目が離せません!
次回『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第9回 「「玉菊燈籠(たまぎくどうろう)恋の地獄」のあらすじ
市中の地本問屋たちが「吉原と手を切る」と言い出し、蔦重(横浜流星さん)は細見などをつくっても、市中で売り広められなくなることを危惧する。
そんななか、鳥山検校(市原隼人さん)が、瀬川(小芝風花さん)を身請けしたいという話を耳にする。そのとき、初めて瀬川を思う自分の気持ちに気付いた蔦重は、ある行動に出る。そして、新之助(井之脇海さん)は、思いを寄せるうつせみ(小野花梨さん)を連れて吉原を抜け出そうと、思い切った計画を立てるが…。
※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』~第8回 「逆襲の『金々先生』」のNHKプラス配信期間は2025年3月2日(日)午後8:44までです。
- TEXT :
- Precious編集部
- ILLUSTRATION :
- 山田シャルロッテ/新刊情報:ママトモ同志【マイクロ】 1 https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=86946
- EDIT&WRITING :
- 河西真紀
- 参考資料:『江戸のきものと衣生活』(小学館)/『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 前編』(NHK出版)/『NHK2025年大河ドラマ完全読本 べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺』(産経新聞出版)/『日本髪の描き方』(エクスナレッジ)/『お江戸ファッション図鑑』(マール社)/『見てきたようによくわかる 蔦屋重三郎と江戸の風俗』(青春文庫)/『江戸の衣装と暮らし解剖図鑑』(X-Knowledge)/『一日江戸人』(新潮文庫)/『蔦屋重三郎 江戸を編集した男』(文春新書) :