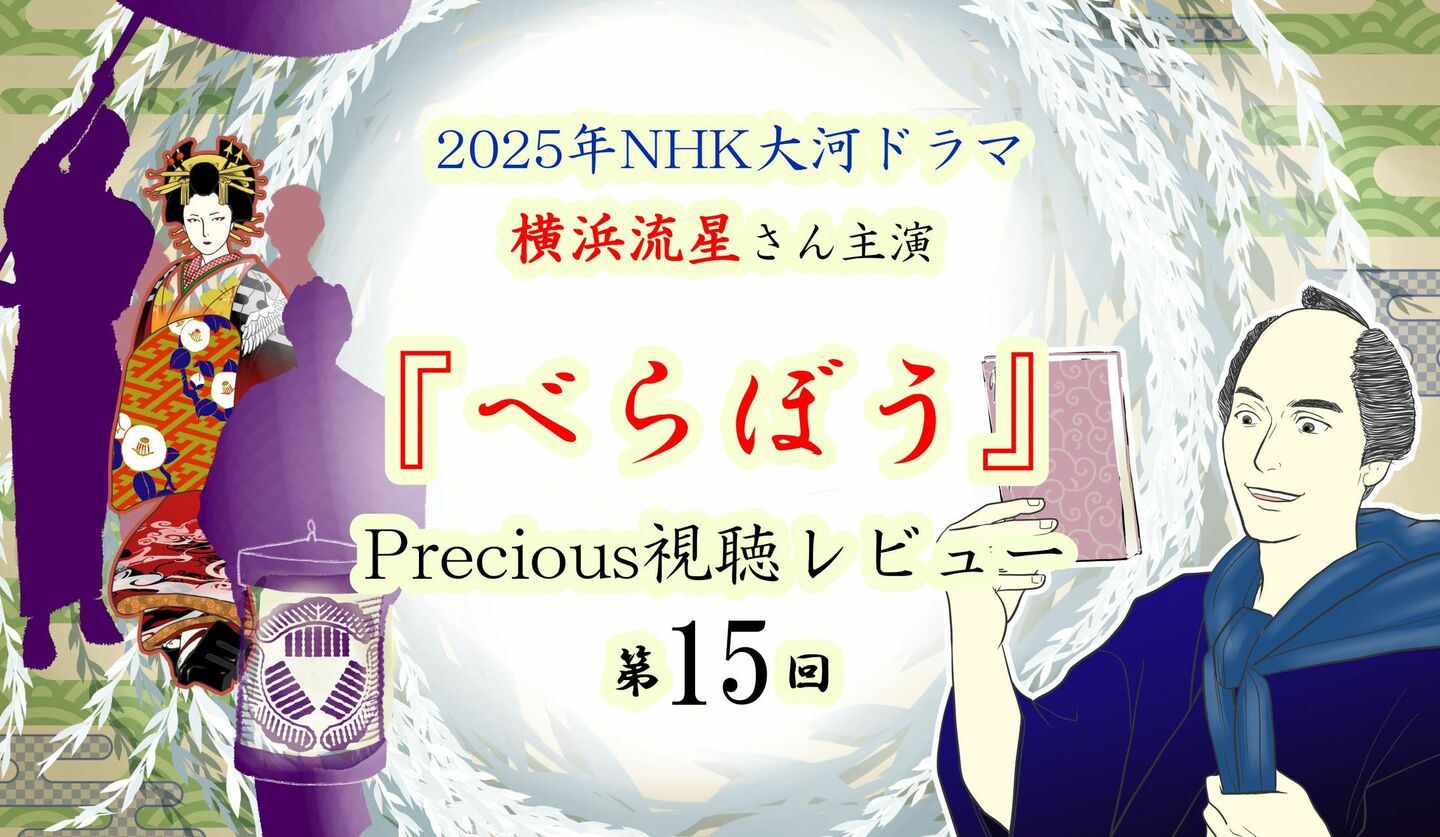【目次】
- 老舗女郎屋「松葉屋」の“いね”は心優しき経営者
- 老舗女郎屋「松葉屋」の“いね”は心優しき経営者
- 蔦重を養子に迎えた「駿河屋」の“ふじ”
- 忘八陣営の紅一点「大黒屋」の“りつ”に先見の明あり!?
- 場末の河岸見世「二文字屋」の“きく”
- 次回『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第16回 「「さらば源内、見立は蓬莱ほうらい」のあらすじ
【これまでのあらすじ】
前々回放送の第14回では、鳥山検校(市原隼人さん)と瀬川(小芝風花さん)の(現代の感覚ではいびつに思えるかもしれないけれど)美しい夫婦愛、瀬川と蔦重(横浜流星さん)のピュアな愛と、ふたつの温かくも悲しげなラブストーリーが一応の完結を見ました。検校の思いに涙、離縁を受けての瀬川の言葉に涙、蔦重のつかの間の喜びにも、瀬川の決意にも涙…第14回は前半戦のひとつの山場だったのだと思います。
『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』は江戸のメディア王となる蔦屋重三郎の立身出世物語ですが、吉原という特殊な街で生きるさまざまな人物の苦悩や、人間味溢れるエピソードがピリリと効いた、極上のエンタメ大河だと確信した瞬間でもありました。
さて、前回の第15回はと言うと…。蔦重は瀬川を失った悲しみのなかでもふたりの夢だった自身の書店「耕書堂」を吉原五十間道で開店、そこに現れた朋誠堂喜三二(尾美としのりさん)は相変わらずのお調子者っぷりを発揮、平賀源内(安田顕さん)は世間からいかさま師呼ばわりされて様子がおかしくなり…。
そんななか、グッとドラマを締めたのが「白眉毛」こと老中首座の松平武元(石坂浩二さん)です。
将軍徳川家治の嫡男、家基(奥智哉さん)が鷹狩りの最中に急逝。その原因を探るなかで浮上したのが、老中・田沼意次(渡辺謙さん)が用意した手袋に毒が仕込まれていたという可能性です。
その手袋を先んじて入手した武元に呼び出された意次は、「自分の失脚を企てる武元にまんまとやられた…」とほぞを噛む思いでしたが、武元はそれを一喝! 「見くびるな。わしがそなたを気に食わんとはいえ、これを機に使い追い落としなどすれば、誠の外道を見逃すことになる。わしはそれほど愚かではない!」。なんとかっこいい! 金の力を信じすぎている意次を諭し、さてこの一件どうするか…という展開でしたが、さすが昭和、平成、令和にわたり活躍し続けている名優・石坂浩二さんと渡辺謙さんです。この松平家の茶室での数分間は、本作の名シーンのひとつだと筆者は断言します!
さて、今回のべらぼうレビューのテーマは「吉原に生きる女」の第2弾です。吉原は「女で遊ぶ男の街=男社会」だと思われがちですが、数こそ少ないものの、遊女以外の女性も男性と肩を並べて活躍した場でもありました。そんな“吉原女”をご紹介します。
【老舗女郎屋「松葉屋」の“いね”は心優しき経営者】
瀬川がいた老舗の女郎屋「松葉屋」の女将は、水野美紀さんが演じるいね。愛想がなく、当時まだ花の井と名乗っていた瀬川に客を5人も6人も取らせたり、うつせみ(小野花梨さん)の足抜けを阻止して厳しい体罰を与えるなど、女郎にも金勘定にも厳しい女将です。
そういった態度をとるのも、自身が元花魁だったからこそ。女郎のつらい気持ちが誰よりわかるからこその厳しさなのです。女郎の多くは親がなかったり親に売られた身。吉原での生活が苦しいものであっても、この街にいる限りその身は守られます。祭りなどひととき浮かれて過ごせる瞬間もあれば、日常のなかにもささやかな楽しみはあります。そうして耐え、よい人に身請けされて大門を出ていくことが女郎の幸せだと信じている、厳しくも心優しき女将なのです。
そして、夫である「松葉屋」主人の半左衛門(正名僕蔵さん)は、吉原の顔役であるもののやり手という印象はなく、影が薄いというかつかみどころがないというか…。「松葉屋」でいねの存在感が大きいのは、半左衛門あってのものとは思いますが…。ちなみに、江戸時代の人のような名前の正名僕蔵さんですが、苗字の正名(まさな)は本名ですが、お名前は文夫さんとおっしゃいます。
【蔦重を養子に迎えた「駿河屋」の“ふじ”】
吉原の女郎屋の経営者たちが何かというと集まるのが、引手茶屋「駿河屋」の2階座敷。忘八たちのサロン的存在でもある「駿河屋」は、主人の市右衛門(高橋克実さん)と、ふじ(飯島直子さん)、跡取り息子の次郎兵衛(中村蒼さん)、そして養子の重三郎(蔦重)で成り立っています。
引手茶屋とは、客を女郎屋に案内する、いわば「吉原遊びの入口」です。「駿河屋」の市右衛門は、気分よくさせて大金を使わせるための客あしらいは蔦重や店の者に任せ、常にしかめっ面。息子たちを殴ったり階段から突き落としたりなんてことは日常茶飯事で、令和なら一発アウトな親父です。
この無鉄砲な行動に出る夫を支えているのが女将のふじ。帳場でそろばんをはじいていたり、何やらポリポリと食べていたりするシーンが多いですね。瞬間湯沸かし器のような夫と、ちょっとのことでは動じそうもない妻。蔦重だけでなく、身寄りのない子どもを奉公人として育てるなど、実は愛情深い夫婦なのです。風流を好む長男次郎兵衛のあののんきな様子は、親の愛情のなせる業、なのかもしれません。
【忘八陣営の紅一点「大黒屋」の“りつ”に先見の明あり!?】
吉原の女郎屋や引手茶屋の主人たちを「忘八(ぼうはち)」と呼びます。これは儒教に由来する8つの徳(仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌)を忘れた者たち、という意味。そういうものを捨て去らなければ幕府公認の廓街は成り立たなかった、ということなのでしょう。
『べらぼう』での忘八のひとりが女郎屋「大黒屋」の女将りつ(安達祐実さん)です。小さな体から発せられる気風のよさが気持ちいいですね。第15回放送で、突然りつは女郎屋を廃業することを宣言。女芸者が客を取らされたり、玉代(ぎょくだい/賃金)を搾取されたりすることを憂い、芸者の取り次ぎや玉代の計算などを引き受ける「見番」をやるというのです。
「金儲けができればよし」と考えていた忘八たちでしたが、蔦重の「吉原を楽しい街、憧れられる街にしたい」という熱い想いや行動に触発され、変えていかなければと一念発起…というわけです。今後の放送では、りつの言動が出版人としての蔦重に影響を与えるよう…楽しみですね。
【場末の河岸見世「二文字屋」の“きく”】
女郎たちが晴れて吉原を出ていくには、身請けされるか、年季が明けるか。ですが、実際には年季が明ける前に病死する女郎も少なくありません。無事に年季が明けても行く当てがなく、下働きに就いて吉原にとどまったり、お歯黒溝(おはぐろどぶ)沿いに並ぶ「河岸見世(かしみせ)」と呼ばれる格式の低い女郎屋に身を寄せる者も。
そんな河岸見世のひとつ「二文字屋」の女将がきく(かたせ梨乃さん)です。かつては吉原の女郎でしたが、年季が明けると「二文字屋」を任されました。さらに厳しい環境に身をさらされる河岸見世の女郎たちに、貧しいながら愛情をたっぷり注ぐきく。蔦重が『一目千本』を出版する際、彼女のもとで働く女郎たちがその制作を手伝っていたのを覚えているでしょうか。瀬川だけでなく、さまざまな“吉原女”の希望の光となるのが蔦屋重三郎という“吉原男”なのです。
【 次回『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第16回 「さらば源内、見立は蓬莱ほうらい」のあらすじ】
家基(奥智哉さん)の急逝した事件は確固たる証拠を得ぬまま幕引きとなる。意次(渡辺謙さん)は源内(安田顕さん)に、これ以上詮索を控えることを告げると、源内は激怒する。
一方、蔦重(横浜流星さん)は源内の住む“不吉の家”と呼ばれる屋敷を訪ね、正月に出す戯作の新作を依頼するも、時折、奇妙な言動を繰り返す様子が気になっていた。そんな矢先、蔦重や意次のもとに、“源内が人を斬った”という知らせが入る…。
※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』~第15回 「死を呼ぶ手袋」のNHKプラス配信期間は2025年4月20日(日)午後8:44までです。
- TEXT :
- Precious編集部
- ILLUSTRATION :
- 山田シャルロッテ/新刊情報:ママトモ同志【マイクロ】 1 https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=86946
- WRITING :
- 小竹智子
- 参考資料:『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 前編』(NHK出版)/『蔦屋重三郎の生涯と吉原遊郭』(宝島社)/『蔦屋重三郎の生涯と吉原遊郭』(宝島社) :