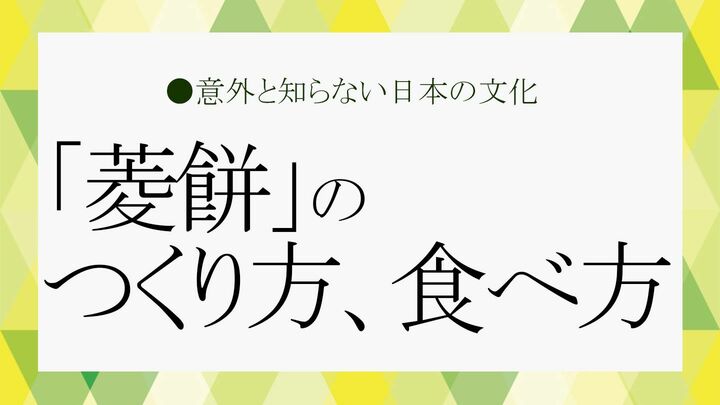ひな祭りに飾る「菱餅(ひしもち)」は、皆さんご存知ですよね。実は「菱餅」は日本の伝統食なんです。でも「食べたことがない!」「簡単につくれるの?」と思った方は多いのでは? 年に1度のひな祭り、せっかくですから「菱餅」も美味しくいただきませんか? ということで今回は「菱餅」をテーマに、由来や飾り方に加え、つくり方や食べ方、そしてそのアレンジまでをご紹介します。
【目次】
【「菱餅」とは?色の「意味」、「由来」】
■菱餅とは?色の「意味」
「菱餅(ひしもち)」は、3月3日のひな祭りに飾られる、菱形に切った餅のこと。別名「雛 (ひな) の餅」。ご存知ですよね。一般的な「菱餅」の色は、赤、白、緑の3色です。 その色にもそれぞれに意味があるといわれていますよ。
赤:「魔除け」「先祖を尊ぶ心」
白:「子孫繁栄」「長寿」「清浄」
緑:「厄除け」「健康」
■「由来」
ひな祭りの起源とされているのは、古代中国の「上巳節(じょうしのせつ)」です。中国では、ひな祭りを行う「上巳の節」に母子草(ははこぐさ)を入れた餅を食べる習慣があり、それが日本に伝わったとされています。母子草とは春の七草のひとつで、御形(ごぎょう)とも呼ばれます。日本では縁起がよくないとれ、邪気を払うヨモギが「菱餅」の緑色に使われるようになりました。
ひな祭りには、女の子の身代わりとして厄災を引き受けてくれる雛人形へ、感謝の気持ちを表すべく、「菱餅」をお供え物として飾ります。 また、ひな祭りに女の子が「菱餅」を食べることで、無病息災や子孫繁栄の祈願になるとされています。
【「菱餅」の基本のつくり方・レシピ】
「菱餅」は見知っていても、「食べたことはない」という人がほとんどでは? ここでは、「菱餅」を自分でつくるための材料やレシピをご紹介します!
■材料・用意するもの
・もち米:3合(約15個分)
・水:360㏄
・片栗粉(打ち粉):適量
・砂糖:少量
・色紅(代用品に赤梅酢でも可)
・よもぎ(代用品として青のりでも可)
・炊飯器
・クッキングシート
・菱形をかたどった型(厚紙などで作ってください)
■つくり方
1. もち米を炊く
もち米をとぎ、水につけたら1時間程度おきます。 そのあと、炊飯器の普通炊きコースで炊飯してください。
2. もち米をつく
もち米が炊けたら耐熱性のボウル(代用品に鍋などでも可)に移します。すり粉木やめん棒などを使い、米粒を擦るように潰します。時々、すりこ木やめん棒などを水で濡らして、もち粒がくっつかないようにしてくださいね。 この際、餅に少し砂糖を入れると、やわらかさが多少保てます。つぶつぶ感がなくなるまで、10分程度ついていきます。がんばって!
3. 色付け
ある程度やわらかくなってきたタイミングで味見をして、なめらかになっていたら、赤、白、緑と3色の分量に取り分けます。赤用に色紅、緑用によもぎを混ぜ、再度味見をしながらお好みに調節します。 もち米のつぶつぶ感がなくなったら、お餅のできあがりです。
4. 菱形にカット
3色の餅を各5個ずつ、計15個の小分けにします。片栗粉をまぶしたクッキングシートの上に餅を乗せ、事前に準備しておいた菱形の型より、少し大きめに伸ばして型押しします。餅が7~8割ほど固まるまで、そのままおきます。急ぎの場合には、サランラップをかけて冷蔵庫で冷やせば時短になりますよ。
固まったら、菱形の型からはみ出した餅を切り取りましょう。 余分な片栗粉を刷毛などを使って落とし、下から、緑、白、赤の三段に重ねれば、「菱餅」の完成です。硬くなり過ぎると切りづらくなり、やわらか過ぎても包丁にくっついて、形が崩れやすくなるので、ご注意を。
【「菱餅」の食べ方】
「菱餅」に関する知識を蓄えたところで…せっかくですから美味しくいただきましょう。
■「いつ」食べる?
「菱餅」は、雛人形へのお供え物です。早くてもひな祭りの当日、もしくは3月3日を過ぎてから食べるのがよい、といわれています。
■縁起のいい食べ方は?
「菱餅」は角をちぎって食べた方が「角が立たずに生きる」ことにつながり、縁起がよいといわれています。また、焼いたり煮たりするとやわらかくなって、ちぎらなくても角が取れるので、より縁起がよいとされているようです。
次に、市販されている「菱餅」を例に、食べる準備をご紹介します。
■「菱餅」を食べる準備その1:まずはお供えする
包装は解かずにそのまま飾りましょう。梱包された「菱餅」は真空パックになっていることが多く、開けてしまうと空気に触れた餅が乾燥して、固くなってしまいます。
■「菱餅」を食べる準備その2:カットして三枚に切り分ける
「菱餅」は3色に分かれているため、その間に包丁を入れると、きれいに切り分けることができます。縁起物といわれている菱餅ですが、包丁を入れても問題ありません。
■「菱餅」を食べる準備その3:食べる前は必ず加熱を
一般的な餅と同じように、お好みで、焼いたり、煮たりなどして食べてください。 梱包された菱餅は、多くの場合は生餅ですから、必ず加熱して食べてくださいね。
【ビジネス雑談に役立つ「菱餅」の豆知識】
■どうして「菱形」?
「菱餅」の特徴的な形である菱形は、「菱」の実が由来とされています。菱とは、葉が水面に浮く一年草の水草で、種子は食用可能。古来より、固いトゲで覆われている菱の実には魔除けの力があると考えられていました。その魔除けの力を餅に込めようと、菱の実を模した菱形になったとされていますよ。また、菱の花の強い繁殖力は、古来の人々に子孫繁栄を連想させたそうです。こうして、「菱餅」は縁起物として扱われ、厄除けや無病息災、子宝を願うひな祭りに食べられるようになったのです。
■「菱餅」の色の順番に意味はあるの?
上記「つくり方」では、「菱餅」の飾り方は上から、赤、白、緑の三段と説明しましたが、実は飾り方はほかにもあり、それぞれ意味合いが異なります。
下から緑白赤:雪の下に新芽が芽吹き、木には桃の花が咲いている様子
下から赤緑白:雪の中から新芽が顔を覗かせ、木に桃の花が咲いている様子
「菱餅」の赤は「桃の花」を、白は「雪や残雪」を、緑は「新緑や新芽」を表現しているとされています。いずれも春の情景(訪れ)をイメージした飾り方で、繊細な感性が素敵ですね!
■「菱餅」の飾り方
繰り返しになりますが、前提として、「菱餅」は、ひな祭りに飾り祀られる雛人形へのお供え物です。本来、雛人形は女の子の厄災を身代わりとして引き受けてもらうために飾るもの。雛人形に対する畏敬の念や感謝の気持ちが、「菱餅」を飾ることにつながったといわれています。「菱餅」を飾る際には、白い和紙を敷いた菱台(三方ともいう)の上に置きます。菱台は一揃えがふたつセットですから、菱餅もふたつ準備しましょう。七段飾りの雛人形にお供え物とする場合、雛段の上から数えて4段目、右大臣や左大臣がいる中央部分に飾ります。
■「菱餅(ひしもち)」食べ方・アレンジレシピ【実食編】
「菱餅」のアレンジレシピをご紹介しましょう。
・焼き餅、安倍川餅(あべかわもち)
切り分けた「菱餅」をオーブントースターなどで過熱します。焼けたら適度にちぎり、お好みのトッピングをつけながらいただきます。一般的な切り餅よりも若干薄いため、簡単にちぎることができますよ。あんこ、砂糖醤油、海苔と一緒にいただくのがポピュラーですが、きな粉とお湯を用意して、安倍川餅にしても楽しめそうです。
・お雑煮
お雑煮の具材として餅の替わりに「菱餅」を使います。一般的な切り餅と違い、赤や緑の餅が色鮮やかで、よもぎ餅の香りも高く、普通のお雑煮とは一線を画す美味しさ! うどんの上にトッピングとして乗せれば、力うどんとしてもいただくことができます。
・おかき
まずは「菱餅」を適当な大きさや厚みにカットし、網などに乗せて約4日間乾燥させます。 その後、200℃程度の揚げ油で色付くまで揚げましょう。揚げたてに塩をふったら完成です。
・揚げだし餅
フライパンを熱し、多めの油を引きます。一口大にカットした「菱餅」を入れ、膨らんできたら裏返し。両面を揚げ焼きすると、さらに美味しくなります。再度裏返して少し経過したところで餅を引き上げ、だし汁に入れていただきます。
・ピザ
ピザ生地の上にカットした「菱餅」を乗せて焼くだけの、簡単餅ピザ。トッピングには、餅に合う和風テイストな明太子や海苔がおすすめです。鶏肉やチーズとも相性がよさそう。
***
いかがでしたか? ひな祭りは女の子の健康と幸せを祈る日本の伝統行事です。お雛様を飾るのは少々面倒ですが、桃の花と「菱餅」、ひなあられなどのしつらえは、いかにも春の風情。見ているだけで和みます。今年は眼福に加え、美味しくひな祭りを楽しんでみませんか?
- TEXT :
- Precious.jp編集部