【目次】
- 摂取目標量は20g! 食物繊維を積極的に摂取して
- コンビニで手軽に買える | 食物繊維の多い「果物」【4選】
- 低カロリーでダイエットにもなる | 食物繊維の多い「野菜」【5選】
- むくみ解消にも効果的 | 食物繊維の多い「芋類」【1選】
- 便秘改善&免疫力アップ | 食物繊維の多い「きのこ類」【1選】
- 水溶性食物繊維が白米の20倍 | 食物繊維の多い「穀類」【1選】
摂取目標量は20g! 食物繊維を積極的に摂取して
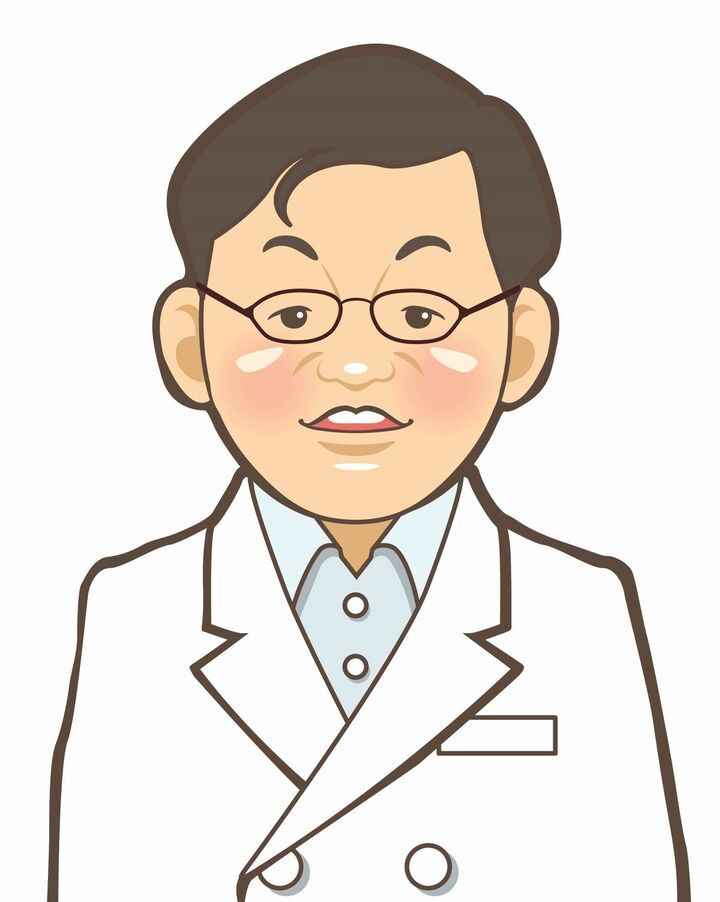
「水溶性」「不溶性」ふたつの食物繊維のベストバランスを知ろう!

QOL(生活の質)の低下や、寿命短縮の可能性のある便秘が、増加している理由のひとつには、食物繊維不足が深刻というのがあるようです。
「便秘予防に勧められる栄養素のひとつとして知られる食物繊維の摂取量は、年々減少しています。摂取目標量は、18〜20gとされていますが、2010年以降は14g前後で推移しており、摂取目標を大きく下回ってしまっています。
食物繊維には、水溶性と不溶性のふたつに分けられます。不溶性食物繊維は、穀類、野菜、豆類、キノコ類、果物などに含まれ、胃や腸で水分を吸収して大きく膨らみ、腸を刺激し、ぜん動運動を活発にすることで便通を促進します。
一方、水溶性食物繊維は昆布、ワカメ、こんにゃく、里芋などに含まれ、大腸内で分解されるとビフィズス菌などの善玉菌が増え、整腸効果をもたらします。
1日に必要とされる水溶性食物繊維はおよそ5g。これら2種の食物繊維のベストバランスは『不溶性2:水溶性1』ですので、意識的に摂ることでお腹の調子を整えていくと良いですね」(松生先生)
コンビニで手軽に買える | 食物繊維の多い「果物」【5選】
【1】キウイ

朝食メニューや夕食後のデザートなど食卓でキウイフルーツを楽しんでいる人に嬉しいニュースが。キウイこそ、便秘解消の救世主スーパーフルーツだったのです!
2016年に世界初のキウイフルーツの国際シンポジウム「キウイフルーツの栄養素及び健康効果に関する国際シンポジウム」が開催され、キウイフルーツの添加後に「酪酸」濃度が増加したという研究結果が発表されるなど、注目が集まっています。
そして、他の果物と比べても、食物繊維量が豊富と言われています。例えば、バナナ1.1g、りんご1.4gに対しグリーンキウイは、食物繊維量が3.0gと倍以上。
また、キウイフルーツは、便の膨張と保水力をアップさせる食物繊維の効果が、他の繊維に比べて高いこともわかっています。
「キウイフルーツは、水溶性食物繊維含有量が多いので、意識的に摂ることで健康増進にもつながります。また、豊富に含まれるのは食物繊維だけでなく、主要な17種の栄養素がどれだけ含まれているかを比較した栄養素充足率スコアでも、キウイはトップクラスです。ビタミンはもちろん、カリウムやアクチニジンなども含む高栄養素でバランスのいいフルーツなのです」(松生先生)
キウイは、手のひらで包むように優しく持ち、弾力を感じるくらいが食べごろ。固いときは、バナナやリンゴなどの「エチレン」を発生する果物と一緒にビニール袋に入れ、室温で2~3日ほど置くと良いそうです(熟してきたら冷蔵庫保管です!)。
下処理の手間がかからず、皮のギリギリまですくって無駄なく食べられるハーフカットは栄養摂取面からもオススメです!
【2】りんご

リンゴに含まれるポリフェノールは抗酸化作用が強く、
意外と知らない!?インナービューティープランナーが教える「デトックス」のウソ・ホント
【3】バナナ


「朝から適度な糖質摂取は体内時計をリセットできて、1日のスタートとしてとても良いですね。バナナは食物繊維も多いので、血糖値の急激な上昇を抑制できますし、お通じにも良いですね。手軽に食べられることも、忙しい朝には適しています。しかし、たんぱく質が足りないので、ヨーグルトやスムージーなど、何かほかのたんぱく質を含む食品と一緒に摂取することがおすすめです」(柳井さん)
ライザップが解説!「平成に流行ったダイエット」は本当に効果がある?成功ポイントは?
【4】グレープフルーツ

食物繊維やビタミンCが豊富な「グレープフルーツ」。
「グレープフルーツは、フロリダ、カリフォルニア、南アフリカと産地が異なるため、通年を通して手に入れることができます。フロリダ産は冬から春にかけて、カリフォルニア産は夏、南アフリカ産は秋が旬です。ホワイトは、柔らかな果肉で果汁も多く、爽やかな酸味が特長。ピンクは、果肉がしっかりとしていて、ホワイトより酸味が少なく食べやすいです。南アフリカ産は、赤色が濃く、酸味がまろやかなんですよ」(岩田さん)
健康寿命をのばしつつ華やか!腸活レシピ【グレープフルーツ編】
低カロリーでダイエットにもなる | 食物繊維の多い「野菜」【5選】
【1】玉ねぎ

冷え性対策のために、毎日の食事にぜひ取り入れてほしい食材が「玉ねぎ」。食物繊維が豊富であるほか、玉ねぎに含まれるケルセチンという成分が内臓脂肪の燃焼を助ける働きがあるのです。あらゆる料理に使える玉ねぎは、常に冷蔵庫にストックしておきたい食材です。
【2】キャベツ

キャベツは食物繊維が豊富に含まれており、整腸作用などに効果を発揮してくれます。また92%が水分であるため、カロリーが低く抑えられるのもうれしいポイントですね。
調理するとグッと食べやすくなるため、スープにすることでたくさんの量を摂取でき、満足感が高いのもメリットです。
【3】セロリ

セロリにも食物繊維やカリウムが多く含まれるため、整腸やむくみ解消にぴったりです。また、シャキシャキとした食感があることで満腹感アップにも一役買ってくれます。スープなどに使う際には、ちょっと食感を残す程度に煮込むとよいでしょう。
【4】アボカド

体の解毒作用を担っている臓器といえば、肝臓。
意外と知らない!?インナービューティープランナーが教える「デトックス」のウソ・ホント
【5】ビーツ

ビーツには食物繊維のほか、天然の難消化性オリゴ糖「ラフィノース」が含まれています。腸内の環境を整えて善玉菌を増やし、悪玉菌の増殖を抑制する効果が期待できます。また便通を改善することで、老廃物を体外に排出しやすくします。
食べる輸血!?スーパーフード「ビーツ」の注目成分NO(一酸化窒素)の健康効果、食べ方、レシピなど
むくみ解消にも効果的 | 食物繊維の多い「芋類」【1選】
里芋

里芋は糖質が少なく、代謝を促すビタミンB群たっぷり!低カロリーで食物繊維(ムチン等)を多み、美肌や便秘解消も期待できます。独特のぬめり成分は、免疫力アップ。粘膜を保護するだけでなく、たんぱく質の吸収をよくしてくれるので肉や魚と好相性です。食物繊維やカリウムも豊富なので、むくみも解消にも効果的。
デトックス効果を狙うなら!お正月は、愛媛の郷土料理「白味噌お雑煮」
便秘改善&免疫力アップ | 食物繊維の多い「きのこ類」【1選】
まいたけ

ウイルス抑制に有効と言われているのは舞茸に含まれるαグルカンの効果によるものとのことですが、他にも免疫力アップにはβグルカンも含有されています。このβグルカンの含有量が、きのこ類でもトップクラスという舞茸! 様々な栄養素が健康をサポートしてくれます。
インフルエンザ予防の際は、αグルカンだけでなく、舞茸に含有されているビタミンDなども相乗効果を発揮しています。
また、MDフラクションと呼ばれる水溶性食物繊維のβグルカンは免疫機能を高め、体の酸化を予防する効果も期待されています。そのMXフラクションや食物繊維、αグルカンなどのおかげで血糖値上昇を抑制する効果や、話題のAGE(終末糖化産物)対策にもなります。豊富な食物繊維のおかげで、便秘改善サポートにも役立ちます。
免疫力を高めてウイルス感染予防をサポート! 知られざる「舞茸」の力とは?
水溶性食物繊維が白米の20倍 | 食物繊維の多い「穀類」【1選】
もち麦

「もち麦には、腸内の善玉菌のエサとなる水溶性食物繊維が豊富に含まれています。白米の約20倍も含まれているので、便秘解消に効果的です。
また、ビフィズス菌とヤセ菌(日和見菌)と呼ばれる腸内細菌が、水溶性食物繊維を発酵分解する際に短鎖脂肪酸を産生するのですが、この短鎖脂肪酸には「脂肪の蓄積を防ぐ」「食欲をコントロールする」「交感神経を刺激して脂肪の燃焼を促す」といった肥満予防の効果も期待できます。
そのほかにも、脂質の代謝に欠かせないビタミンB群や、体内の水分バランスを保つカリウムなどのミネラルも含まれているので、腸内環境を整えるならオススメの食材です」(岩田さん)
- TEXT :
- Precious.jp編集部



















