【目次】
- 「ビタミン」が豊富な食べ物【6選】
- 「ポリフェノール」「リコピン」など抗酸化作用のある食べ物【5選】
- 「イソフラボン」の豊富な食べ物【3選】
- 「たんぱく質」「βカロチン」など代謝が上がる食べ物【4選】
「ビタミン」が豊富な食べ物【6選】
【1】じゃがいも
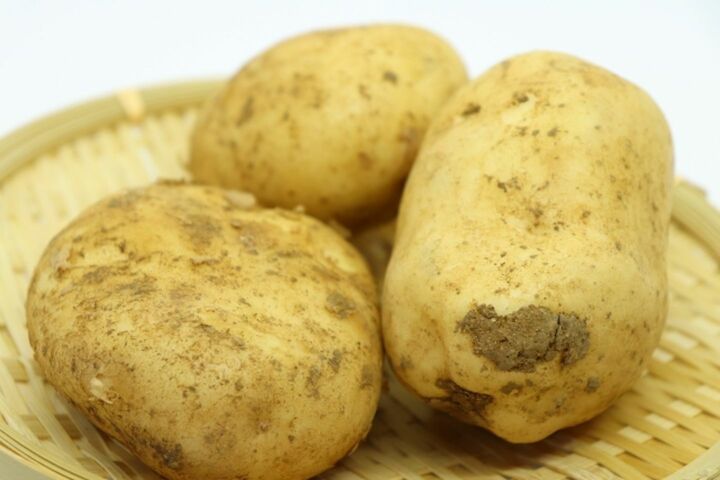
じゃがいもにたっぷり含まれる、ビタミンCは美肌に欠かせない栄養素として知られています。ビタミンCは、肌に弾力やハリをもたらすコラーゲンの生成に欠かせないため、積極的に取り入れたい食材のひとつ。本来、ビタミンCは加熱することで壊れやすくなりますが、じゃがいもに含まれているビタミンCは「でんぷん」に包まれた状態なので、熱を加えても壊れにくいのが魅力。茹でても、ビタミンCを効率的に取り入れられるので、美肌効果が期待できます。
ビタミンCたっぷりの「じゃがいも」×はちみつで仕上げる「アカシアハニーのポテトサラダ」
【2】ゴマ

胡麻にたっぷり含まれるビタミンEは、皮膚を整えてくれるビタミンのひとつ。メラニン色素がシミに変化するのを防ぎ、コラーゲン生成をサポートしてくれます。美容のビタミン剤とも呼ばれる胡麻は、紫外線が強くなる季節に積極的に取り入れたい食材です。
栄養価の高い「はちみつ」で仕上げる、さっぱり酢の物「アカシアハニーのきゅうりと油揚げの胡麻酢和え」
【3】キウイ

免疫力に欠かせないビタミン群、特にCやE、そして食物繊維などが豊富に含まれており、1日の摂取推奨量や目安量・目標量といった値はほとんどが、超えている、または近い数値となっています。1個あたり50~60kcalの低カロリーで、血糖値に影響しにくい低GI食品でもあるので、ビタミンなどの栄養素が欠乏しやすいダイエット中の人にもおすすめできます。
専門家3名が提唱! withコロナ生活のカギとなる免疫力アップに期待できる「キウイ」のパワーとは?
【4】マッシュルーム
見た目もコロンと可愛らしく、ローカロリーなビタミンB2が豊富なマッシュルーム。ビタミンB2は肌を整える効果もありますが、糖質からエネルギーを作る時にも大活躍。ダイエットで脂肪を燃やしたいときにも欠かせない、女性に嬉しいビタミンです。
美肌に欠かせないコラーゲンが豊富!「鶏手羽元とみかんジュースのブレゼ」の簡単レシピ
【5】大根

冬野菜の定番大根は、消化酵素ジアスターゼがたっぷり。新陳代謝を良くして、美肌効果を期待できます。また、大根はビタミンCも豊富!コラーゲン生成をサポートして、肌のハリを保ちます。メラニン色素を抑制して、美白効果に繋げるなど肌に嬉しいことだらけ。
1月3日は『三日とろろの日』!体が優しく温まる「生姜の香る、麦みその豚汁」レシピで胃腸を整えて
【6】みかん

みかんは、抗酸化作用のあるビタミンCが豊富に含まれています。ビタミンCは、単体で取っても体に吸収されにくいとも言われていますが、みかんに含まれるスペリジンという成分が吸収率をアップ。乾燥などの肌トラブルを抑制します。美白効果も期待できるビタミンCの他、腸を整える食物繊維、疲労回復効果を期待できるクエン酸も含まれています。
美肌に欠かせないコラーゲンが豊富!「鶏手羽元とみかんジュースのブレゼ」の簡単レシピ
「ポリフェノール」「リコピン」など抗酸化作用のある食べ物【6選】
【1】アーモンド

栄養素の豊富なアーモンドですが、抗酸化物質が豊富に含まれている食品のひとつであり、ナッツのなかでは最も多くビタミンEが多く含まれているのも大きな特長といえます。ビタミンEに加え、リボフラビン、亜鉛、ナイアシンなどの様々な栄養素も含まれるので、アーモンドを摂取することは、ビタミンEを摂取することで健康でいきいきとした肌を保つことができます。
今こそ取り入れたい! 「アーモンド」の秘めたる美容効果とは?
【2】アスパラガス

アスパラガスは、高い抗酸化力を誇る野菜として知られています。アスパラギン酸という成分が有名ですが、これはその名のとおり、アスパラガスから発見された成分。エネルギー代謝を活発にし、疲労回復に効果的です。また、アスパラガスには、抗酸化ビタミンと呼ばれるβ-カロテン・ビタミンC・ビタミンEがすべて入っています。美容食材として取り入れたいのはもちろん、彩りも鮮やかで一気に華やかな印象に。
良質なタンパク質で美しい髪へ!簡単ヘルシーな「仔牛の和風ブランケット・ド・ボー」レシピ
【3】セロリ

食物繊維が豊富で、腸にも優しいセロリ。レタス1個で食物繊維が約2.8gといわれているのに対し、セロリ1本で約2.3gもの食物繊維を含んでいます。スープや煮込み料理には欠かせない香味野菜としても知られていますが、腸を整えてくれるので美肌にも効果的。また、セロリにはビタミンC・ビタミンEが含まれるので、活性酸素の発生や酸化力を抑える効果も。血管の老化を防ぎ、肌のハリや潤いを保ちます。
お腹すっきり!「腸活」におすすめの食材とおうちごはんレシピ4選
【4】トマト

トマトに多く含まれるリコピンは、抗酸化作用によるアンチエイジング効果を発揮。彩りの華やかさを添えるだけでなく、活性酸素を抑制し美しい肌へと整えます。
むくみ解消にもお役立ちレシピ!「抹茶そうめんとトマトのカッペリーニ風」
【5】オリーブオイル
抗酸化作用があるとして知られるオレイン酸は、オリーブオイルに豊富に含まれています。年齢を重ねるごとに、カラダの抗酸化力は弱まってしまうもの。オリーブオイルを摂取することで、オレイン酸のもつ抗酸化作用が働き、シミ・シワ・たるみなど気になる部分のエイジングの加速を抑制します。
むくみ解消にもお役立ちレシピ!「抹茶そうめんとトマトのカッペリーニ風」
「イソフラボン」の豊富な食べ物【3選】
【1】納豆

“納豆菌×大豆”を組み合わせた納豆は、腸活にとって理想的な食品のひとつ。というのも、納豆菌などの善玉菌(プロバイオティクス)は、食物繊維やオリゴ糖を多く含む食品(プレバイオティクス)と一緒に摂ると腸内環境改善に効果的。納豆は食べ過ぎると、大豆イソフラボンの過剰摂取になるおそれもあります。納豆のみで考えると、1日2パックまでは大丈夫とも考えられますが、ほかにも豆腐や豆乳などの大豆製品を摂る可能性を考えると、1日1パックを目安にしたほうがよいでしょう。
腸活で免疫力アップ!管理栄養士に聞いた「発酵食品の効果的な食べ方」
【2】味噌

味噌は、生命維持に必要な必須アミノ酸が多く含まれます。ときには「飲む美容液」と呼ばれることも。肌の保水力をアップする働きがある、グルコシルセラミドもたっぷり! 味噌を摂取することで、作られるセラミドは、肌の潤いをキープをサポートします。
発酵食品とはちみつパワーで免疫力アップ! 保存がきく「はちみつ味噌玉」と「はちみつで炊くふっくらご飯」レシピ
【3】黒豆きなこ

黒豆きなこは、ポリフェノールが多く、アンチエイジングに効果的。黒豆は抗酸化作用が強く、老化の原因となる活性酸素の発生を抑制します。シミやシワなど肌の老化を抑える効果も。きな粉は大豆イソフラボンやレシチンなど、女性に嬉しい栄養が満点!月経前症候群や生理不順、更年期症状などの女性の悩みにアプローチする食材です。ミネラルたっぷりの黒糖と併せてどうぞ。
スイーツでアンチエイジング!?簡単「黒豆きな粉の黒糖シュガートースト」レシピ
「たんぱく質」「βカロチン」など代謝が上がる食べ物【4選】
【1】ヨーグルト

体にいいとされる発酵食品で、たんぱく質が多く含まれているヨーグルト。糖質や資質の代謝を促進させるビタミンB2も豊富です。また、ヨーグルトに含まれる乳酸菌は、腸内環境を整え、便通が良くなることで肌トラブルの解消にも。
【2】生姜
生姜は、血流をよくするので体がポカポカ温まります。代謝がアップすることで、体内の循環がスムーズになり、むくみも解消。溜まった毒素が排出されることで、美肌効果も期待できます。
【3】ニンジン
にんじんは、コラーゲンの生成を助けるビタミンCやβカロテンが豊富に含まれています。油と合わせると、βカロテンの吸収もアップ。美肌・美髪へ導くだけでなく、視力維持、粘膜や呼吸器を守る働きもある優秀食材です!
1月3日は『三日とろろの日』!体が優しく温まる「生姜の香る、麦みその豚汁」レシピで胃腸を整えて
【4】オーツミルク

オーツミルクとは、オーツ麦からつくられる植物性ミルクのこと。オートミール同様、食物繊維のほか、たんぱく質やカルシウムが豊富で、さらにビタミンDやビタミンB群などが添加された、栄養価の高い食品です。また、GI値が低いことも、からだにいい、とされています。
スタバもいち早く取り入れた「オーツミルク」とは?ブレイク間近の理由を解説!
- TEXT :
- Precious.jp編集部



















